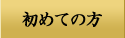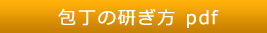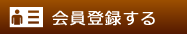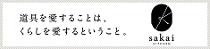堺の技
緞通
堺の敷物の中でも「緞通」は、江戸時代から近代にかけて盛んに生産された手織物です。真田紐を製造していた糸物商、藤本庄左衛門が、中国、佐賀の鍋島の緞通を参考にしてつくりだしたといわれています。
織機の前に座り、黙々と手を動かすのは堺緞通の技術伝承者。 まっすぐに張られた縦糸に、横糸となる色糸を指先で結びつけ、左手に持ったはさみで切ります。「トルコ結びとペルシャ結びの2種類があってそれぞれに特長があります。今、やっているのはトルコ結び。模様が鮮明に立ち上がります。織るのはとても単純な作業なんですよ」。こともなげに言いますが、細かな指先の動きと流れるような作業は、まさに手技の仕事です。
設計図は方眼紙に描かれたデザイン図、その図から起こす数字がずらっと並んだ票。どの段の何番目に、どの色を何目入れるかを示しています。それらを見ながら一目一目結んでいきます。左手には独特の「握りハサミ」。これも刃物の町、堺でつくられた特別なハサミ。安全なように刃の先端が平たく、毛足を刈り込みやすいように持ち手と刃の間に段差がつくられています。一段を織り終えると、織機に付いている筬(おさ)という木で上から叩くように抑える「筬(おさ)打ち」をします。そうすることで目の詰まった丈夫な緞通になります。さらに毛をまっすぐに立たせるために櫛を入れ、木を当てて毛足を刈り込みます。少しずつ少しずつ織り上げられていく模様。6畳物を3人で1日織っても約8センチしかできないという、とても根気のいる仕事です。
堺緞通は今、堺式手織緞通技術保存協会を中心に、講習会を開催しするなど技術伝承者を養成。堺伝統産業会館などでその作業を見学することができます。
昆布
まろやかな昆布と酢の香りが迎えてくれました。シャッシャッシャッと手で昆布を削る音が絶えない作業場。今、細かく削る「とろろ昆布」はほとんどが機械でつくられていますが、薄くて幅が広く、ふんわりと口の中でとろけるような「おぼろ昆布」は、職人が一枚一枚、手で削る以外にはできません。
おぼろ昆布削りは20分ほどで包丁が切れなくなるそう。そのために替え刃を何本も用意しています。職人さんが砥石で研ぎ、刃を付け直す。そのときに「アキタ」という道具を使い、刃先を少し曲げます。自分の手に合う角度に調節していくのが難しく、切れる包丁がつくれて一人前だそうです。
昆布の端を足で押さえ、片手で引っ張り、もう一方の手に持った包丁で削りますが、力の入れ加減で厚さが変わるので、薄く均一にするのが腕のみせどころ。その薄さはなんと0.05mm ! 削る前に手で触った感覚で何回、包丁が入るかがわかるようになるそうです。白い部分、褐色の部分でも味が変わります。白い部分だけを集めたものは太白おぼろと呼ばれる最高級品です。両面を削り、最後に白い芯を残します。これはお寿司のバッテラの上に乗っている薄い昆布用の商品になります。寿司店によってそのサイズの指定があり、いくつもの木の型が掛けられていました。
「最初の頃は手を切ったり、すべって足をケガしたり。でも痛さを知って、どうすれば防げるようにもっていくか。ケガしてなんぼです(笑)」と職人さん。
遥か江戸時代に北海道の昆布が瀬戸内海を経て、堺に到達。大阪という大消費地を控え、加工に必要な刃物の特産地でもあり、堺は昆布加工の一大産地となりました。機械生産が増えましたが、おぼろ昆布は昔と同じ方法で、堺の手が伝統の味を継承し続けています。
線香
工場に入る前から、馥郁とした空気に包まれました。線香の香りはどこか懐かしく、心を穏やかにしてくれます。天正年間(16世紀)には中国から製法が伝わり、堺ですでに製造されていたとされるほど長い歴史を誇ります。技を受け継ぎ、機械化も取り入れ、伝統の中で進化してきました。
タブの木の葉、枝、皮、芯を粉状にしたタブ粉に、沈香や白檀、丁子などの天然香料を、家伝の処方で調合し練り上げた原料が、機械を通して押し出されてきます。幾筋もの細い糸状のものを木の盆で受け、竹べらで切る「盆切り」。それを右手の竹ベラですくい、手の甲に乗せて、乾燥板へと移し並べていく「生(なま)」という作業。重なったものや途中で切れた線香を慎重に取り除きます。細く、長く、柔らかいものを、つぶさぬように、重ならないように扱う、手の技。リズミカルに、スピーディーに、よどみなく続けられていきます。
板からはみ出した部分を切り、必要なサイズに切っていく「胴切り」。丸いカッターでなんと半分だけ切るときも。「約2mmの径なら半分の1mmまで刃をいれて止めます。力を入れずすっと切るだけです」と職人さんは語りますが、微妙な力加減は高度な技ならではでしょう。線香に曲がりは許されません。ある程度乾燥した時点で、すき間を詰めて曲がりを防ぐ「板寄せ」。板を両手で持ち、一瞬、ふるうだけ。この作業が一番、難しいといいます。「化学糊を使わず、木の粘りだけですからもろい。乾燥してすき間ができると曲がってしまいますから、寄せてぴたりと揃えます」。
線香づくりは一見するとどれもシンプルな作業です。シンプルだからこそ難しい。手で、身体でそのコツを会得していくのでしょう。仏事やお墓参り用だけでなく、今や部屋の癒しの香りとしても親しまれている線香。芳香の中に手技が息づいています。
注染
伝統的な手染めの染色技法、注染。表裏両面から染めるので木綿糸の芯まで染まり、鮮やかな色合いと色あせしにくいという特徴があります。
注染は防染糊を置く「糊置き」から始まります。大きな器に入った防染糊は、土と天然の布海苔を混ぜたもの。糊置きは、型紙を生地にあて、その上から糊をつけた大きな木のへらで、均一に薄く塗る作業です。職人さんは軽々と生地に置いていきますが、糊は弾力があり、力とこつの要る作業。使い込んだへらの握り部分は職人さんの指の形に凹んでいました。
糊置きを終えると、そそぎ染め「注染」へ。熟練の職人は50種類ほどの染料を調合し、無限の色合いをつくり出すそう。染色台の向こう側に、大小様々の染料を注ぐ道具「どひん」が並んでいます。まず防染糊が置かれていない白い生地の周りに、これも防染糊で「土手」をつくります。この土手の中に染料を注ぎこんで染めるのですが、複雑な柄になると十数種類の色を使い分けるそう。注染独特の技法である「ぼかし」は奥行きを感じさせ、プリントでは出せない味わいが表現できます。濃度の異なる染料を注ぐ、繊細で高度な手の技。「何十年やってもまだ勉強しています」とベテラン職人さん。
染め上った生地は水洗いし「立て干し」へ。かつてはすぐそばを流れる石津川で洗っていたそうです。豊かな川のめぐみも堺の注染を発展させた大きな要因です。染められた生地が立て干しされ、心地よさそうに風に揺れていました。「水洗い以外はほとんど手作業。機械化したいけれどできないんですよ」と語ります。趣味手拭いやゆかたブームもあり、多種様々な注文に丹念に、確かに応えていくことで全国有数の産地となった堺の注染。京都の高級料亭のフキン、人気キャラクターやご当地手拭い、海外有名ブランドのエコバッグ生地など、国内外で幅広い用途で使われるようになり、堺の注染はますます注目を集めています。
和菓子
桜、椿、バラ、菜の花に鶴……。職人の手から次々と創り出されていく和菓子の造形に目を見張ってしまいました。道具類もさまざま。刃物の町、堺ならではの製菓用専用ハサミ、羊羹包丁などはもちろん、和菓子専用の数々のヘラ、馬の尾の毛を張った漉し器、どこの家庭にもあるスプーンや箸も使い、柔らかな曲線をつくるために卵をきゅっと押し当てる。圧巻は製菓用ハサミで花びら一枚一枚を切っていく「菊切り」。講習など人前でするときはベテランでも緊張するという繊細な技。見る間に白いおまんじゅうに大輪の菊が咲き誇りました。そんな仕事ぶりを見ていると、最大の道具は指、手のひら。堺の手だと気づきます。
千利休が大成した茶の湯文化、南蛮貿易によって良質な砂糖や芥子(けし)の実などが集まってきたことが、堺の和菓子文化のベースにあるといわれています。
丸める、包む、伸ばす、型を抜く……。餡や練り切りといった材料は長く触れていると温かくなるのでスピードが命。さっささっさと手が動き、同じ意匠、同じ分量のものが並んでいきます。季節によって生地の整え方も変わり、生地の柔らかさ加減も手で感じる。手は温度計でもあります。もちろん、繊細な作業と同時に、餅を揉み、餡を練るという力仕事も職人の手の仕事です。
「お菓子で季節を表現するのは世界でも日本だけだと思います。それも少し先取りして店頭に並べる。もう桜の季節か、お彼岸、お盆、お月見、紅葉と暦を知らせる。世界遺産に登録された和食と並ぶ、素晴らしい和菓子文化だと思います」と職人は語ります。
茶席菓子、餅菓子、焼き菓子、もなか、落雁、和風のスイートポテトから飴類まで。熟練した職人の技から生まれる多彩な堺の和菓子が、日々の暮らしに彩りを添えます。
刃物
堺打刃物のルーツは5世紀中頃までさかのぼります。世界最大の前方後円墳である「仁徳天皇陵古墳」の造営のために全国から職人が集まり鋳鉄技術が伝えられたことにはじまります。
堺打刃物は堺市とその周辺地域で、高度に発達した鍛冶技術と刃付けと呼ばれる研ぎの技術で製造された包丁やハサミの総称です。鍛冶、刃付けは完全分業制で、それぞれがいくつもの複雑な工程を経て、見事な切れ味と美しさを備え、正に火と鉄と水による工芸品と賞賛されています。
最初の工程は「鍛冶」。赤く熱した地金(軟鉄)に、刃金(鋼)とを合わせ、炉で熱し鍛接し半型をつくります。それをハンマーでたたき包丁の形を整え、焼なまし、荒たたき、焼入れ、焼戻しなど、刃金の硬度を高めて切れ味を鋭くするとともに、地金に粘りを持たせて欠けにくい刃にしていきます。 次の工程が「研ぎ」。荒研ぎ、本研ぎ、歪み取り、裏研ぎ、刃あて、バフあて、小刃合わせの工程を経て最終仕上げの刃を付けます。
最後の工程が「柄付け」。中子を加熱し木柄に差し込み後端を木槌でたたきます。
料理は包丁の切れ味で、味も見た目の美しさも大きく変わります。包丁は使っているうちに切れ味が悪くなってきます。そこで大切なことは家庭での「研ぎ」。家庭では包丁を研ぐのは難しいと思いこんでいる人も多いようですが、コツさえ掴めばいつまでも切れ味抜群の包丁を使い続けることができます。
伝統工芸士でもあるプロの研ぎ職人さんにコツを教えていただきました。「まず、砥石は荒砥、中砥、仕上げの3つがあり、すべて揃えるのが理想的ですが最低、中砥は常備しましょう。和包丁の特長は片刃で、はがねの見えている部分が少ない。皆さん、この部分だけ?とよく聞かれますが全体に入っています。両刃は表裏いっしょに見えますが、すべてにはがねが入っています。それを砥石で研ぎ出していく。堺の包丁は研ぎ方さえ間違わなければ一生使えますよ」。